これは、10回目の採卵で「OHSS(卵巣過剰刺激症候群)予備軍」と診断された、私の体験談です。
AMH(抗ミュラー管ホルモン)の値も低めで、これまで一度もOHSSを指摘されたことがなかった私にとって、それはまさに「予期せぬ出来事」でした。
「自分はなりにくいタイプだから大丈夫」
そんな風に思い込んでいた採卵の当日、経験したことのない激しい痛みに襲われました。うずくまって動けないほどの痛みと、「このままどうなってしまうんだろう」という強烈な不安。
この記事では、そんな私が激痛を越え、医師から告げられた「入院」を回避するために、実際にクリニックから受けた指示や、自宅で実践したセルフケアについて具体的にお伝えします。
「自分は大丈夫」は禁物。私のOHSS体験談
まさか私が?OHSSを他人事だと思っていた理由
その採卵は、私にとって10回目となるものでした。これまで何度も採卵を経験してきましたが、OHSSと診断されたことは一度もありません。
私のAMH(抗ミュラー管ホルモン)の値は、1.25 とどちらかといえば低め。一般的にOHSSは、たくさんの卵胞が育つPCOS(多嚢胞性卵巣症候群)の方や、AMHが高い方に多いと聞いていたので、「自分はリスクが低いタイプ」と、どこかで安心しきっていました。
今回の採卵周期は、卵胞を育てるために「レコベル」という自己注射を使い、排卵を抑えながら卵を育てる「ショート法」でのぞみました。これまでと違う薬を使う認識はありましたが、それがOHSSに繋がる可能性については、深く考えていませんでした。
採卵当日からの異変と、医師からの突然の宣告
異変は、採卵が終わって麻酔から覚め、診察室に呼ばれた時に始まりました。
いつも通り採れた卵子の数の報告だろうと思っていた私に、医師から告げられたのは予想外の言葉でした。
「卵巣がかなり腫れていますね。OHSS予備軍です。ひどくなると入院になる可能性があるので、症状を抑える薬を出しておきます」
痛みもまだそれほど強くなく、自覚症状がほとんどなかった私にとって、それは突然の宣告でした。治療として、これ以上症状が悪化するのを抑えるための「ガニレスト」という注射を処方され、その日は帰宅しました。
うずくまるほどの激痛。電話をためらった夜
本当の恐怖が訪れたのは、家に帰ってからでした。
時間が経つにつれて、下腹部にズキズキとした鋭い痛みが出始め、夜にはピークに達しました。
 ぶー奈
ぶー奈これはやばい。もう動けない…
まるで、採卵で使ったあの長い針が、ずっとお腹の中に残っていて、子宮を刺し続けているような激痛。
あまりの痛みに、思わずうずくまって動けなくなりました。お腹もパンパンに張っていて、いつも履いているズボンがウエストのあたりできつく感じます。



クリニックに電話した方がいい…?
頭をよぎりましたが、「このくらいの痛みで大騒ぎしていいんだろうか」というためらいもあり、すぐに電話をかけることができませんでした。
処方されていた痛み止めの「ロキソニン」を服用。「これで1時間経っても痛みが治まらなかったら、その時は絶対に電話しよう」と心に決め、ただひたすら痛みが引くのを待ちました。
幸い、薬が効いてくれたのか、1時間ほどで刺すような痛みは少しずつ和らいでいきました。しかし、「明日もこの痛みが起こったら無理なのでは?」という不安はありました。
【医師の指示】OHSS予備軍の私が自宅療養で守った3つのこと
採卵後の激痛はロキソニンで何とか乗り切ったものの、お腹の張りと鈍い痛み、そして再発への不安は続いていました。医師から告げられた「入院」という言葉を避けるため、私はクリニックからの指示を徹底的に守ることに決めました。
私が自宅療養中に特に意識して実践したのは、次の3つのことです。
1. 水分補給は「義務」と心得る
医師から最も強く言われたのが、「とにかく水分をしっかりとってください」ということでした。
OHSSは血液中の水分が血管の外に漏れ出てしまうことで、血液がドロドロになり、血栓症(エコノミークラス症候群)のリスクが高まる状態。それを防ぐために、水分補給は不可欠です。
スポーツドリンクを用意して、「喉が渇いたから飲む」のではなく、「義務」として飲むようにしました。具体的には、1時間にコップ1杯のペースでこまめに口にするよう心がけました。
2. 安静にしつつも「少しだけ」動く
「基本は安静に。でも、家の中を少し歩くぐらいは動いた方がいいですよ」
これも、血栓症予防のための大切な指示でした。痛みが怖いからと一日中ベッドで寝たきりになるのは、逆効果になる可能性があるとのこと。
痛みがひどい時はもちろん無理せず、横になって休みました。そして、少し楽になったタイミングを見計らって、意識的に家の中をゆっくりと歩くようにしました。
例えば、トイレに立つ、キッチンまで飲み物を取りに行く。そんな些細な動きだけでも、「体を固まらせない」という意識を持つことが大切だと感じました。
3. 体のサインを見逃さない「尿チェック」
「もし、尿がほとんど出なくなったら、それは危険なサインです。すぐに連絡してください」
これは、医師から言われた最も具体的な受診の目安でした。
腹水が溜まることで体内の水分バランスが崩れると、腎臓へ行く血液が減り、尿量が極端に減少することがあります。
幸い、私はそこまでの症状には至りませんでしたが、トイレに行くたびに「ちゃんと出ているか」「量は極端に少なくないか」をセルフチェックする習慣がつきました。
自分の体の変化を客観的に観察することは、漠然とした不安を「大丈夫、まだ正常な範囲だ」という安心感に変える効果もあったように思います。
今だから言える、OHSS予防のために「やっておけば良かった」こと
幸いにも私のOHSSの症状は、ガニレスト注射と自宅療養によって徐々に落ち着き、入院を回避することができました。採卵から2日後にはあの刺すような激痛はなくなり、日常生活を送れるまでに回復しました。
振り返ってみて、今回のつらい経験から学んだことがあります。それは、次の採卵に向けて実践しようと心に決めた「予防策」です。
採卵前から「高タンパク・減塩」の食事を意識する
症状の改善には、血液中の水分を保つ働きのある「タンパク質」を多く摂り、体に水分を溜め込みやすくする「塩分」を控えることが効果的だと言われています。
日々の食事に少しだけ気を配って、サラダチキンをプラスする、いつもの食事に納豆や豆腐を一品加える、といった小さな改善を行なっています。
「症状が出てから」慌てて対策するのではなく、「症状が出る前から」体を整えておく。その少しの意識が、未来の自分を助けてくれるはずです。
自分の体質を過信せず、医師に不安を伝えておく
「AMHが低いから、自分は大丈夫」
この思い込みが、私の油断に繋がっていました。今思えば、10回目の採卵で初めて使う排卵誘発剤もあったのですから、これまでと違う反応が起きる可能性は十分にあったのです。
次の採卵では、たとえリスクが低くても診察の際に「OHSSになるのが少し心配です」と、自分の気持ちを素直に伝えてみようと思います。
そうすることで、医師もより注意深く経過を診てくれるかもしれませんし、私自身も「もしかしたら」という心の準備ができます。専門家と不安を共有することは、最良のリスク管理の一つだと、今回の経験を通して痛感しました。
まとめ:OHSSは誰にでも起こりうる。だからこそ正しい知識と準備を
10回目の採卵で経験した、予期せぬOHSS(卵巣過剰刺激症候群)の症状。
「自分は大丈夫」という思い込みがいかに危険であるか、そして、終わりが見えない痛みと不安の中で過ごす時間がどれほどつらいものか、身をもって知りました。
「このくらいの痛みで電話していいのかな…」その一瞬のためらいが、対応を遅らせてしまうかもしれません。いつもと違う痛み、急激な体重増加、尿量の減少など、少しでも異変を感じたら、どうか自分を責めずにクリニックに連絡してください。



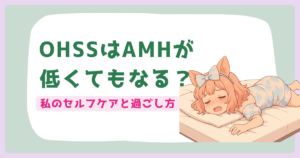
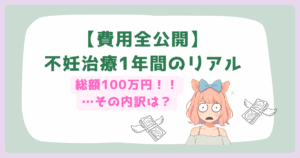
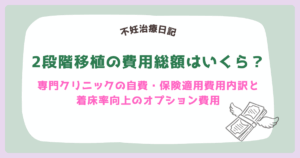
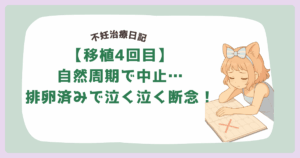
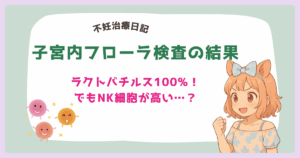
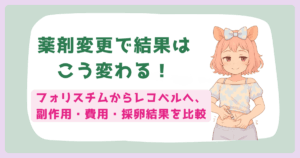
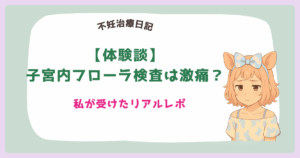
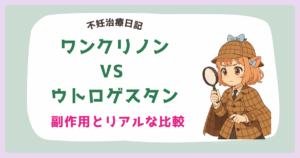
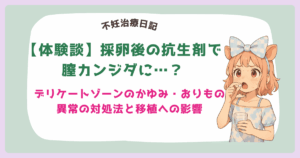
コメント